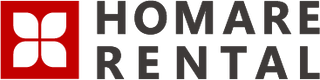スタンド看板(自立式看板)は、手軽に設置でき視認性も高く、店舗やイベントで幅広く活用されています。本記事ではその正しい設置方法、注意点、活用シーン、レンタルと購入の違いなどを徹底解説します。
スタンド看板が選ばれる理由と設置の重要性
お店の前やイベント会場で目にする「スタンド看板」。設置するだけで人の目を引き、誘導・案内・PRと多くの目的を果たすこのアイテムは、販促や運営の現場で欠かせない存在となっています。
とくに短期間で設置・撤去が必要な催事や展示会では、その“手軽さ”が大きな武器になります。看板を掲げるだけで視認性が上がり、道行く人に店舗やイベントの存在を効果的に伝えることができるからです。
しかし、その一方で「設置の仕方を間違えると、風で倒れてしまった」「うまく視線を集められなかった」「思ったより目立たない」など、設置ミスや選定ミスによるトラブルも後を絶ちません。
本記事では、こうした“もったいない使い方”を防ぐために、自立式看板の正しい設置手順と注意点を詳しく解説します。さらに、レンタルと購入の使い分け、タイプ別の選び方などもご紹介し、初めての方でも迷わず設置できるようにナビゲートします。
「短期だけどしっかり見せたい」「手間なく設置して安心して使いたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
1.スタンド看板とは?種類と特徴を徹底解説
スタンド看板とは、地面に直接設置でき、特別な支柱工事や穴あけを必要としない看板の総称です。A型タイプやポール付きタイプなど多彩な形状があります。ここでは、代表的なスタンド看板看板の種類と、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
1-1. A型スタンド看板
「A型看板」は、名前の通りアルファベットの“A”の形状をした看板で、2枚のパネルを蝶番でつなぎ、開いて自立させるタイプです。

✅ 特長
・非常に軽量で持ち運びが簡単
・折りたたみが可能で収納性も高い
・両面印刷やポスター差し替えが可能なタイプも
✅ 用途例
飲食店のランチメニュー表示、美容院の価格案内、展示会場での案内板など、屋内外問わず幅広く使われています。
✅ 注意点
風に弱いため、屋外で使う場合はウエイト(重し)必須。素材もプラスチック製からアルミ製までさまざまあり、耐久性に差が出ます。
1-2. 直立看板
「直立看板」は、看板表示面が上部もしくは全面にあるタワー型の看板です。垂直に立つスタイリッシュな形状で、本体自体に重量があるタイプと、下部に水や砂を入れることで重しとなるベースを備えたタイプがあります。

✅ 特長
・看板自体の高さがあり、遠くからでも目立つ
・本体重量で安定するタイプと、注水式ベースタイプがある
・タワー型でスマートな印象を与える
・片面・両面使用可能なタイプがある
✅ 用途例
駐車場誘導、工事現場の注意喚起、店舗の遠距離視認目的、商業施設でのブランディング 表示などに活躍します。
✅ 注意点
注水式ベースタイプの場合は、ベースの注水忘れ・漏れによる転倒リスクあり。本体重量タイプも強風時は注意が必要。
1-3. LED付きスタンド看板
夜間営業やイベントなど、視認性が求められるシーンで選ばれるのがLED付き看板です。

✅ 特長
・内部または上部にLED照明を内蔵し、夜間でも明るく目立つ
・デザイン面も光によって強調され、訴求力が高い
・防水仕様で屋外にも対応可能
✅ 用途例
飲食店の夜間営業、屋台やナイトイベント、パチンコ店などで多く採用されています。
✅ 注意点
電源確保が必須。ケーブルの取り回し、屋外での感電防止処理、充電式かコード式かも要チェックです。
1-4. L型看板
斜めに傾斜した形状が特徴的な「L型看板」は、設置面積がコンパクトでありながら効果的な表示が可能な看板です。イーゼルのように斜めにパネルを掲示するスタイルで、安定感に優れています。

✅ 特長
・斜めの傾斜により視認性が高い
・設置面積がコンパクトで場所を取らない
・キャスター付きタイプは移動が簡単
・スタイリッシュなデザインで高級感を演出
✅ 用途例
商業施設の通路、クリニックや美容関連店舗の案内、ショッピングモールのエントランス、飲食店のメニュー表示など、さまざまな場所で活躍
✅ 注意点
傾斜角度が固定されているため、設置場所の視線の高さを考慮する必要あり。キャスター付きの場合はストッパーがあるかを確認。
1-5. 比較表:主要タイプ一覧
| 画像 | タイプ | 特長 | 耐風性 | 持ち運びやすさ | 屋外対応 | 重しの必要性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
A型スタンド | 両面表示・折りたたみ式 | △ | ◎ | ○ | 必要(屋外) |
 |
直立看板 | 高さがあり注目度高 | ◎ | △ | ◎ | タイプによる |
 |
LED看板 | 夜間対応・電源必須 | ○ | △ | ◎ | 必須 |
 |
L型看板 | 斜め表示・コンパクト | ○ | ○ | ○ | タイプによる |
2.設置手順とそのコツを具体的に解説
2-1. A型スタンド看板の設置手順
手順1:地面の状態を確認する
設置面が水平で滑りにくい素材であるかをチェック。アスファルトやタイルなどは問題ありませんが、砂利道や傾斜のある場所は不安定になりやすく要注意です。
手順2:看板を開く
折りたたみ式であれば、蝶番を展開して看板を立ち上げます。ネジがある場合は緩んでいないか確認します。
手順3:内容の表示をセット
ポスターやメニューなどをパネル内に差し込みます。防水・UV対応の透明カバーがあると長期使用に便利です。
手順4:重しを設置
屋外で使用する際は、ベース部分にウエイト(専用の砂袋やタンク)を載せて安定させます。市販の重し以外でも、ペットボトルに水を入れて対応することも可能です。
手順5:通行の妨げにならないよう配置
歩道や出入口では、人の動線や視線を遮らないように配置。片側通行での視認性を意識すると、効果的な誘導が可能になります。
2-2. 直立看板の設置手順
手順1:看板タイプの確認 本体重量タイプか注水式ベースタイプかを確認します。注水式の場合は、水または砂をベースに注入します。容量に対して8割以上を目安に入れると十分な安定感を確保できます。
手順2:パネルと表示板を組み立て 説明書に従ってパネルを本体に取り付け、上部に表示面を固定。クランプがある場合は、しっかりと締めてぐらつきがないか確認します。
手順3:向きと角度を調整 看板の表示面がまっすぐ正面を向くように調整します。風を受け流す角度にすると転倒リスクも軽減されます。
2-3. LED看板の設置手順
手順1:電源の確保 設置場所近くに電源があるかを確認します。延長コードを使用する場合は、屋外対応の防水タイプを選び、コードの取り回しを安全に行います。充電式の場合は事前に満充電にしておきましょう。
手順2:本体の組み立てと配線 LED看板本体を組み立て、電源コードやバッテリーを接続します。屋外使用の場合は、電源部分の防水処理が適切かを確認してください。
手順3:点灯テストと調整 実際に点灯させて、明るさや表示内容が適切に見えるかをチェック。夜間使用の場合は、周囲への光の影響も考慮して角度を調整します。
手順4:安全対策 電源コードが通行の妨げにならないよう配線し、必要に応じてコードカバーやテープで固定します。
2-4. L型看板の設置手順
手順1:設置場所の確認 L型看板は斜めに傾斜するため、通行人の視線に合わせて設置位置を決めます。歩行者の目線の高さを考慮して配置しましょう。
手順2:本体の組み立て パネル受けとトップキャッチ部分を確実に固定し、表示パネルをスライドして挿入します。
手順3:安定性の確認 キャスター付きの場合はストッパーをかけ、重心が安定しているかを確認します。
2-5. 設置時の共通ポイント
⚠️ 設置前に天候を確認
風速5m/sを超える予報の日は、屋外設置は避けるか補強が必要です。
🛠️ 使用道具の事前準備
六角レンチ、滑り止めマット、水平器、延長コード(LED用)など
📏 目線高さを意識した配置
通行人の視線高さ(約140〜160cm)に合わせると効果的
3.安全面・運用面から見る注意点
看板は「人目を引く」ことが目的である一方、安全性も重要な要素です。転倒や衝突などの事故を防ぐため、以下のような注意点を把握しておきましょう。
3-1. 強風・悪天候への備え
🌪️ 風速の目安と設置可否
風速3m/s以上:重し必須
風速5m/s以上:固定追加または撤去推奨
風速8m/s以上:設置自体を中止推奨
⛱️ 風よけ工夫
建物の影・ガードレールの内側など、自然の風除けを利用して設置位置を選ぶと転倒リスクが下がります。
🌧️ 防水処理
ポスター面が濡れると見栄えが落ちるだけでなく、フレーム内に水が溜まりやすくなります。防水フィルム、ビニールカバーなどを併用しましょう。
3-2. 歩行者・車両との距離感
看板は通行人の視線を集める反面、配置を誤ると通行の妨げになるリスクがあります。
🚶歩道設置の際の配慮
最低でも人がすれ違える60cm以上のスペースを確保。歩道の幅が狭い場合は、設置を見送る選択も必要です。
🚗 駐車場・車道沿いでの注意
看板が車の死角に入ると事故の原因になりかねません。車の進行方向とは逆側に置くなど、車両からの視認性にも配慮が求められます。
3-3. メンテナンス・衛生面の注意点
🧽 定期的な拭き掃除
砂ぼこりや鳥のフンがつくと印象が悪くなるだけでなく、フレームの腐食を早めます。中性洗剤+柔らかい布で優しく拭き取るのがベストです。
🔧 ネジ・パーツの点検
移動や折りたたみを繰り返すと、ネジが緩みがちです。月1回を目安に増し締めチェックを行いましょう。
🛡️ 保管方法
使わない期間は屋内や倉庫に収納し、直射日光や雨を避けることで寿命が延びます。折りたたみ型なら専用バッグに収納すると◎。
4.使用シーン別おすすめと実例
スタンド看板は、その設置の手軽さと視認性の高さから、あらゆる現場で活用されています。この章では、主な使用シーン別にどのようなタイプが適しているか、実際の利用例とともに紹介します。
4-1. 屋外短期イベント(展示会・フェス・催事)

特徴とニーズ
- 期間限定の開催で設置・撤去のしやすさが重要
- 一時的な誘導や案内を効率よく行いたい
- 天候対応力が求められる
おすすめ看板
- 直立看板(重し付き)
- A型折りたたみスタンド(軽量で搬入搬出がラク)
活用例
- 食フェスでの出店案内:「◯◯ラーメンはこちら」など
- 展示会場でのゾーン区分:「Bゾーン→」「受付はこちら」
4-2. 店舗常設ディスプレイ

特徴とニーズ
- 毎日使うため、耐久性とデザイン性が求められる
- 内容の更新がしやすいと便利(季節メニューや割引案内)
おすすめ看板
- 直立看板(重し付き)
- L型看板やLED看板(夜間営業店舗に)
活用例
- 飲食店のランチメニューや新作ケーキの案内
- 美容室の料金表・予約受付表示
4-3. 夜間営業や照明が必要な環境

特徴とニーズ
- 通行人の目に留まりやすい
- “光”が重要
- 電源の確保やコード取り回しの工夫も必要
おすすめ看板
- LED内蔵型看板(充電式 or 電源接続タイプ)
- 上部照明付きのスタンドタイプ
活用例
- 居酒屋やバーの営業時間・おすすめメニュー表示
- 24時間営業の店舗案内や誘導表示
4-4. 公共施設・地域案内用

特徴とニーズ
- 屋外の使用が多く、耐久性と防水性が最重要
- 多言語表記や地図入りなど、情報量の多さにも対応
おすすめ看板
- 直立看板+重し固定
- ワイドタイプのA型パネル
活用例
- 公園や観光地の案内板(「現在地→展望台はこちら」)
- 地域イベント会場の配置図表示
5.レンタル vs 購入 — ケース別比較と判断基準
スタンド看板の導入を検討する際、「購入するか」「レンタルで済ますか」は大きな分岐点です。それぞれのメリット・デメリットを整理し、判断の基準を明確にしましょう。
5-1. レンタルのメリット・デメリット
メリット
- 初期費用を抑えられる
- 設置・撤去まで業者に任せられる場合が多い
- 短期間利用に向いている(数日〜1ヶ月程度)
デメリット
- 長期使用になると割高になる
- デザインや仕様の選択肢が限られる
- 汚損・破損時の保証や弁償が必要になることも
5-2. 購入のメリット・デメリット
メリット
- 長期利用でコストパフォーマンスが高い
- 自由な表示内容・仕様を選べる
- 短納期でオンライン注文できる製品も多い
デメリット
- 初期費用がかかる(1台1万〜3万円程度が相場)
- 保管スペースが必要
- 破損時は自分で修理・交換が必要
5-3. ケース別おすすめ判断ガイド
| 利用シーン | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 3日間の展示会 | レンタル | 設置・撤去も任せられる |
| 1年中店頭で使用 | 購入 | 長期利用でコスト回収できる |
| 季節イベント(月1回) | レンタル(定期契約) | 管理不要で便利 |
| 自分で自由にデザインしたい | 購入 | 好きな仕様を選べる |
6.スタンド看板についてよくある質問(Q&Aコーナー)
スタンド看板の設置や運用について、実際によく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。これから導入を検討する方は、ぜひ参考にしてください。
Q1. スタンド看板の設置にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 一般的なA型看板やポールスタンドであれば、設置は5〜10分程度で完了します。初めてでも組み立て説明書があれば問題なく対応できます。
Q2. 強風の日でも使えますか?
A. 重しをしっかり設置すれば通常の風(風速3〜5m/s)には耐えられますが、風速7m/s以上の強風が予想される日は設置を見合わせるか、撤去をおすすめします。
Q3. 雨の日の設置は大丈夫?
A. 屋外対応製品であれば基本的に問題ありません。ただしポスター類が濡れないように、透明ビニールカバーや防水フレームを使うと安心です。
Q4. 夜間の電源確保はどうすればよいですか?
A. LED看板を使用する場合、延長コードを使うか、充電式バッテリー内蔵タイプを選ぶと便利です。防水対応のコードを選ぶことも忘れずに。
Q5. 初心者でも設置できますか?
A. はい、特別な工具や知識がなくても設置できます。折りたたみ式や差し込み型など、誰でも使える設計になっています。
Q6. 固定するために地面に穴を開ける必要はありますか?
A. スタンド看板はすべて「穴あけ不要」で使用できるのが特徴です。重しや滑り止めマットで固定する構造です。
Q7. 汚れたらどうやって掃除すればよいですか?
A. フレームは中性洗剤と柔らかい布で水拭きすればOK。金属部は乾拭きで錆びを防ぎましょう。ポスター面は専用カバーを使用すると汚れにくくなります。
Q8. 看板の内容を頻繁に変えたいのですが…
A. ポスター差し替え式の看板が最適です。フレームを開けて中身を入れ替えるだけで、季節やイベントに応じた運用が可能です。
Q9. 看板を処分したい場合、どうすればいいですか?
A. 一般的な家庭ゴミでは出せないため、「不燃ごみ」または「粗大ごみ」として自治体に相談しましょう。レンタルなら返却のみでOKです。
Q10. 周囲との調和に気をつけたいのですが、どんな工夫がありますか?
A. 周囲の色味に合わせたフレームカラーや、木目調など景観に馴染むデザインを選ぶと良いでしょう。あえて目立たせない選択も一つの戦略です。
まとめ
スタンド看板は、設置のしやすさ、視認性、コストパフォーマンスに優れた販促・案内ツールです。しかし、その効果を最大限に発揮するためには「正しい設置」と「用途に合った選定」が必要不可欠です。
この記事では、代表的な看板の種類と特徴、設置手順、安全対策、シーン別のおすすめ活用法、さらにはレンタルと購入の比較まで幅広く解説してきました。
✅ 短期間のイベントや展示会にはレンタルが便利
✅ 長期的に使用する予定がある場合は購入がコスト的に有利
✅ 設置場所の天候・地面・通行人の動線をしっかり考慮する
まずは、使いたいシーンと期間を明確にし、最適な選択をしてみましょう。
スタンド看板の購入・レンタルはこちらから
ご用途に応じて、スタンド看板は「購入」と「レンタル」の両方に対応しています。
いずれもオンラインから簡単にお申し込み可能です。用途や使用期間に応じてお選びください。